
目次
1. はじめに
こんにちは、進学空間Move塾長宮脇です。
今日は少し重いテーマについて考えてみたいと思います。
先日、「教育虐待」というタイトルの漫画を手に取りました。とあるルポルタージュを漫画化したもので、現在2巻まで出版されているようです。
この作品に触れ、塾の教育者として日頃から感じていることについて、皆さんと共有したいと思います。
2. 本文
教育虐待とは、過度な教育や勉強のさせすぎによって、子どもの心身のいずれかを追い込んでしまう状態のことを指します。
しかし、この問題を考える際に見落としてはならないのは、なぜ親御さんがそのような状況に子どもを追い込んでしまうのか、つまり、親御さん自身が何かに追い込まれているのではないか、という視点です。
子どもが精神的に傷つくことは当然深刻な問題ですが、親御さんの置かれている状況にも目を向ける必要があると思うのです。
私が今まで接してきた中で、いわゆる「教育虐待」的な状況に陥ってしまっている親御さんには、共通して何らかの強いプレッシャーがあるように感じます。
親御さん自身が幼少期に受けてきた教育環境からの影響や、現在置かれている社会的立場からのプレッシャー、あるいは家庭内での義父母との関係性からくるストレスなど、親御さん自身も何らかのプレッシャーにさらされているケースが非常に多いのです。
教育虐待的な状態が子どもにとって良いはずがありません。私たちMoveの生徒たちを見ていても、ただ無理やり勉強させることで成績が上がったり、真の学力が身についたりするケースはほとんどありません。
結局のところ、本人の意思、本人の選択によって学習に取り組む状態が理想的です。親御さんも頭ではそれを理解しているものの、現実の厳しさから目を背けられないという葛藤があるのでしょう。
そのような状態から親御さんがいかに脱却するか、そのためにも私たち教育に携わる人間がいると感じてもらえたらと思います。
少なくとも、Moveにきちんとお子さんが通っているのであれば、勉強については僕たちに丸投げしてもらって構いません。
親御さんが負っているプレッシャーや責任の一端を塾が担います。
そのための塾があっていいと考えていますよ。
3. まとめ
私たち塾の教育者は、この問題から目を背けるのではなく、真正面からぶつかっていく必要があります。
子どもたちの健やかな成長があってこそ、その先に学力の向上があるということを忘れてはなりません。
この問題については語り出すといくらでも話せるのですが、今回はここまでとさせていただきます。
皆さんの教育観を見つめ直す機会になれば幸いです。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


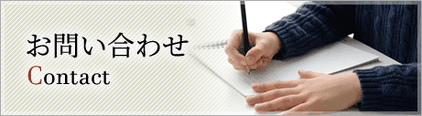
コメントをお書きください