目次

画像はAIによって生成されたものです。実際の様子とは異なります。
1. 想像を超える厳格な世界
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
前回は広島商船高専での寮生活についてお話ししましたが、今回はHくんが所属するボート部について詳しくお聞きしました。
正直、その厳しさは私の想像をはるかに超えていました。
でも同時に、なぜそこまで厳格なのか、その理由を知って深く納得もしたのです。
「先生、ボート部って本当にガチガチなんです」と苦笑いするHくんですが、その表情には確かな誇りも見えました。
全国大会2連覇という輝かしい実績の裏には、想像を絶する努力と責任感があったのです。
2. 1年生の試練と全国2連覇の重圧
まず驚いたのが、1年生の役割です。
部活は4時半開始ですが、1年生は3時半には練習場所に行かなければなりません。
つまり、授業が2時半に終わってから1時間で着替えや移動を済ませ、準備に取りかからなければならないのです。
「オールなどの準備をするために、部活が始まる1時間前から1年生は来ないといけません」とHくん。
この準備時間の間に、先輩が来るまでにすべての準備を終わらせ、艇庫の掃除も完璧にしなければなりません。
そして、その要求水準が半端ではありません。
「鳥の糞が落ちているとか、扉についているとか、そういうことも全部掃除しないと、先輩はよく見ていて、少しでもあったら『1年なのでできない』みたいな感じで注意されます」
私が「それができていなかったら殴られそうな世界ですね」と言うと、「殴るということはないんですが、先輩の目がすごくきついです」とHくんは答えました。
物理的な指導は一切なく、あくまで教育的な範囲での厳格な指導が行われています。
しかし、その精神的な緊張感は相当なもののようです。
この厳しさには明確な理由があります。
今年のボート部は全国大会2連覇を達成した強豪チームなのです。
「ボート部がある学校数がそもそも少ないので、他の人から見たら『しょぼくない?』と思われるかもしれませんが、実際のレースでは圧倒的な差がありました」とHくんは説明してくれました。
確かに、競技人口が少ないからといって、その技術や努力が軽いわけではありません。
現在の部員数は1年生17人、2年生6人、3年生10人。特に1年生が多いのが特徴的です。
「1年生は辞める人もいるんですが、今年の僕ら1年生は多分辞めないですね。雰囲気も結構いいです」とHくんは話してくれました。
厳しい環境でありながら、仲間との結束は強い。
これこそが、この部活の真の魅力なのかもしれません。
3. 練習の実態と命への責任感
実際の練習は、基本的に4時半から6時までの1時間半。
大会の1週間前などは6時半まで延ばすことができ、その場合は2時間の練習となります。
そして練習後には筋トレが待っています。
「筋肉がないとやっぱり部活ができないので、筋肉をつけたい人は自主的に来いという感じです」とHくんは説明しましたが、実際には半強制的な雰囲気もあるようです。
「筋トレ中は本当に、どんなにきつくて上がらなくても『夢を追い込め』という感じで『ほら、ほら』と言われて、ガチガチでやっています」
確かに、久しぶりに会ったHくんは以前より随分逞しくなっていました。
「だいぶ筋肉がついてきた気がします。高校生の体という感じです」と本人も実感しているようです。
私が「怖いけれど、でもそれぐらいしないと命の危険がある世界かもしれませんね」と言うと、Hくんは深くうなずきました。
実際、ボートは海上で行うスポーツです。12人の漕ぎ手が左右に並び、4メートル余りのオールで水をかくカッター訓練は、単なるスポーツではありません。
元々は救命艇として使われていたもので、海難事故の際には人命救助に直結する技術なのです。
「一つのミスが仲間の命に関わることもある」という意識が、この厳格な指導の根底にあるのです。
だからこそ、準備段階から完璧を求められ、妥協は許されない。
この責任感こそが、商船高専のボート部が持つ独特の文化なのです。
4. 仲間との絆と成長への実感
興味深いのは、消灯後の過ごし方です。
本来なら11時が消灯時間ですが、せっかく友達の部屋が近くにあるので、学校生活に支障が起きない程度まで起きていることが多いそうです。
「いつも同じ部活の人で集まるので、部活のときに何か分からないことがあったら、みんなで話し合って解決していこうという感じです」
厳しい練習の中で生まれた疑問や不安を、仲間同士で支え合って乗り越えていく。
この横のつながりが、厳格な縦社会を補完し、部全体の結束を生み出しているのです。
「正直、辞める人もいるのですか?」という私の質問に、Hくんは「辞める人もいますが、今年の僕ら1年生は多分辞めないですね」と答えました。
その理由を聞くと、「雰囲気が結構いい」ということでした。
厳しい中にも、先輩たちの温かさや仲間との絆があり、何より自分自身の成長を実感できているからです。
筋肉がついただけではありません。
時間管理能力、責任感、そして仲間と協力する力。
これらすべてが、普通の部活動では得られないレベルで鍛えられているのです。
このボート部での経験は、単なる高校時代の思い出以上の意味を持っています。
将来、船舶職員として働く際に必要な「責任感」「協調性」「危機管理能力」を、実践的に身につけているのです。
海の上では、一人のミスが全員の命に関わります。
だからこそ、高校時代からこのような厳格な環境で訓練を積むことが、将来への大きな財産となるのです。
Hくんの表情を見ていると、確かに大変そうですが、同時に充実感に満ちています。
「きついけれど、やりがいがある」という言葉が、すべてを物語っているような気がしました。
厳しい指導の中にも教育的配慮があり、生徒の安全と成長を最優先に考えた環境が整っているからこそ、このような素晴らしい成果が生まれるのでしょう。
次回最終回は、卒業後の進路について詳しくお話しします。
外航船で年収2000万円も夢ではない船乗りの世界、そしてどんな人が商船高専に向いているのか、Hくんの実体験を通してお伝えしたいと思います。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


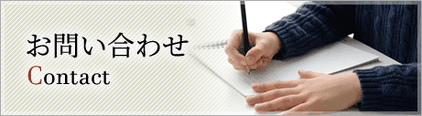
コメントをお書きください