目次

こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今日はある中学3年生の取り組みを紹介させてください。受験生というと、どうしても目の前の問題集や過去問に追われがちですが、この生徒さんはちょっと違うアプローチをしているのです。
1. 受験勉強の傍らで取り組む「ことばの学校」
その中学3年生の女の子は、受験勉強の傍ら「ことばの学校」に取り組んでいます。
これは、リアルの紙の本を読みながら、タブレットから流れてくる朗読を同時に聞くという読書推進ツールです。
たくさんの本を読んで、多くの世界を知りつつ、語彙力を高めていこうという狙いがあります。
1冊読んだら偏差値が1ポイント上がるというような即効性のあるものではありませんが、じわじわと学力の基盤を強化していく方法なのです。
本を読むことは、やはり長期的に学力を高めることに貢献してくれるでしょう。
2. 幼児から高校生まで対応できる豊富なラインナップ
「ことばの学校」の受講生は、通常小学生が多いのですが、中学生にも当然効果がありますし、ラインナップには高校生でも難しい本が入っていたりします。
今Moveにあるラインナップは150冊!
その中から自分に合うものを選んでもらえるのです。
ちなみに、この女の子が今読んでいるのは『資本主義という不思議な仕組み』(佐々木毅著、ちくまプリマー新書)です。
資本主義のルーツを古代ギリシャから紐解き、現代社会の仕組みと問題点を明らかにしようとする本なのです。
一方で、中学1年生の2人は語彙力強化のために、『ずっこけ3人組』や『若おかみは小学生!』といった小学校高学年用の物語を読んでいます。
さらに、小学校低学年の子たちは絵本を読んでいます。
楽しみながら行う語彙力強化にはピッタリですね。
このように、それぞれの年齢やレベルに合わせて選書できるのも、この教材の素晴らしいところなのです。
3. なぜ読書が学力向上につながるのか
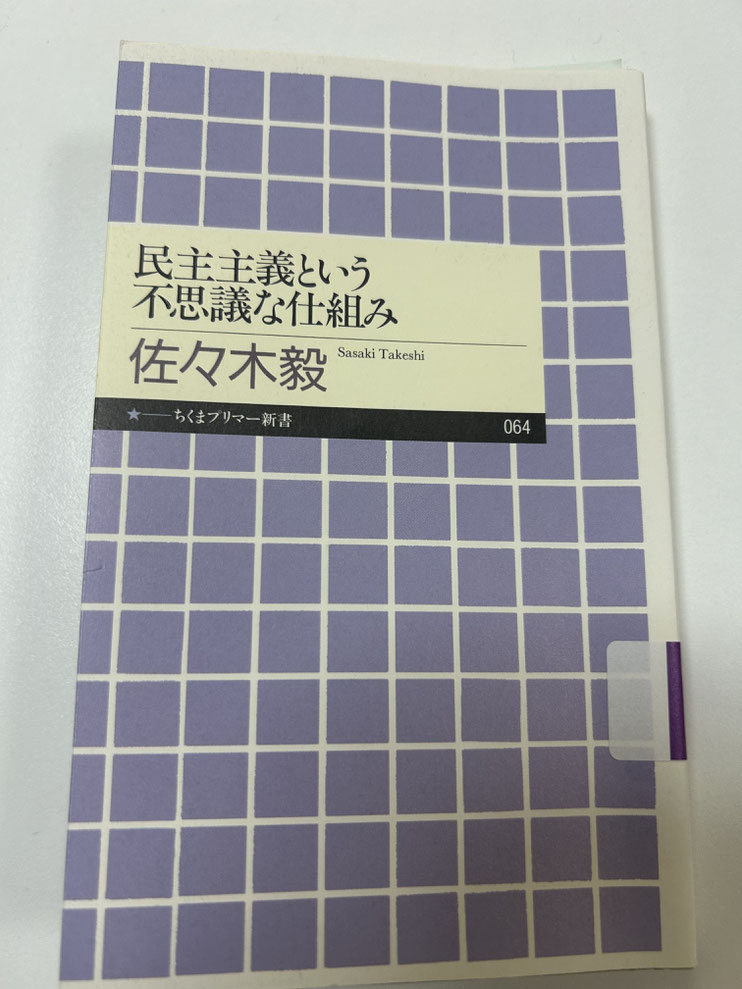
『資本主義という不思議な仕組み』でいえば、こういう本を読んでいると、自然と中学生の「公民」分野や、高校生の「政経」は強くなるでしょうね。
だって、教科書に書いてあること以上の深さで世の中を知ることになるのですから。
読書の効果には、さまざまなものがありますが、その一つに自分の身の回りでは体験できない世界を知るというのがあります。
勉強をしていて困ることの一つに、教科書に書かれていることが想像できないということがありますが、読書を通じてさまざまな世界を知ると、教科書の内容も理解しやすくなるでしょう。
そもそも世界を知るということそのものが学力が上がるという現象と言えるのです。
想像してみてください。
古代ギリシャの民主政治について学ぶとき、その時代の社会や人々の暮らしを知っている生徒と、教科書の文字だけで理解しようとする生徒では、どちらが深く理解できるでしょうか?
読書を通じて得た豊かな背景知識が、学習内容をより身近で理解しやすいものにしてくれるのです。
4. 無理なく学力を上げる新しいアプローチ
現在は、小学生5名と、中学生3名が「ことばの学校」を受講しています。
料金は週に1回50分で月6,000円です。
中学生であれば、個別演習中に好きな時間に読んでもらうこともできます。
勉強ではなくて読書で学力を無理なく上げたい人にはおすすめですよ。
受験勉強に追われる中でも、こうして視野を広げていく取り組みって、きっと将来の財産になると思うのです。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


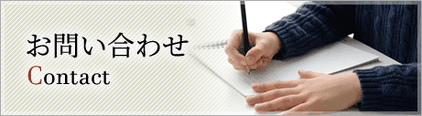
コメントをお書きください