目次

1. 基町から附属への進路変更
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
4回シリーズでお届けしているK君インタビューの第2回目です。
前回は、なぜ海外大学を目指すようになったのか、その背景にある日本社会への率直な想いをお伝えしました。
今回は、なぜ基町高校から附属高校へ進路を変更したのか、そして附属高校での充実した3年間について詳しく聞いてみました。
前回お話しした「考える力」がどのように具体的な行動に現れるのか、そして保護者の皆さんにとって参考になる「子どもの自立を促す環境選び」について、K君の体験を通してお伝えしていきます。
2. 海外進学を見据えた高校選択
「元々は基町に行く予定だったんですけど、その後の進路を考えたら、附属の方がいいんじゃないかという相談を宮脇先生としまして、その結果、附属に進学しました」とK君は振り返ります。
彼とそうした話をしたのはよく覚えています。
では、なぜ基町高校ではなく附属高校だったのでしょうか。
「僕は海外の大学に進学したいっていうのが中3の時から思ってて、それを考えたときに、基町は国立大に行く人たちが多いし、そのための課題の量がたくさん出るっていうのを聞いてたんです。
それをこなすより、自由な附属に行って、自分のやりたいことを伸び伸びやった方が、海外の大学には近いんじゃないかという話をしました」
これは実に戦略的な判断でした。
ここで保護者の皆さんに注目していただきたいのは、K君が「周りがやっているから」ではなく、「自分の目標に最適な環境はどこか」という視点で高校を選んでいることです。
国立大学進学のための画一的なカリキュラムよりも、自由度の高い環境で自分の興味を追求する方が、海外大学進学には有利だという考えです。
そして実際、この判断は大正解だったと言えるでしょう。
3. 合格発表の瞬間
附属高校の合格発表の瞬間について聞いてみました。
「あまり褒められることではないんですが、学校のタブレットでみんなと一緒に見まして、それでみんなで『おー』って言って。
結構な自信があったんですけど、クラスにもう1人友達で一緒に受けた子がいて、その子も受かってて、2人ともみんなで喜んでました」
いかにも中学生らしい率直さですね。
自信があったとはいえ、合格の瞬間はやはり嬉しかったでしょう。
友達と一緒に喜べたのも良い思い出になったと思います。
4. 体育祭のマスゲームで感じた感動
附属高校で最も印象に残っている活動について聞くと、即座に「体育祭ですね」という答えが返ってきました。
「体育祭でマスゲームっていうのがあって、YouTubeとかで調べたら出てくるんですけど、伝統のある集団行動みたいなやつなんです。
それを入学や進級してから1ヶ月ぐらいに配属があって、希望した人がマスゲームに入って、2ヶ月間ぐらいもうぶっ通しでマスゲームしかしないみたいな生活を送って、本番で感動して涙、涙、涙で」
2ヶ月間、マスゲームに集中する生活というのは想像を絶します。
そこまでの情熱を注げる環境があることこそが、附属高校の真の魅力なのでしょう。
「特に高2の体育祭が終わったその日の夜に来年用のグループLINEができるんですよ。
それで衣装とか曲決めとか、ルールも最初は自分たちで作ろうと、全部曲決めて、体型の動きは、マスビジョンっていう先輩が作ったソフトがあって、パソコンで集団行動を作るんです」
驚くべきことに、先輩たちが独自にソフトまで開発しているとは。
これこそが附属高校の自由な校風と、生徒たちの創造性を物語っています。
5. 多様な役割を担った高校生活
K君は高3でマスゲームのうたげ(宴)部に所属し、打ち上げなどを担当したそうです。
「多人数うたげ(宴)っていう打ち上げとかを担当する部で、主に打ち上げを担当したりします。
本格的に高1・高2が集まった練習が始まった後は、前夜祭と後夜祭と、本体打ち上げと各部の打ち上げとか、結構やることがあって、打ち上げ係とは言いつつ、プラスでTシャツを作ったり、トートバッグを作ったりしました」
ここからが本当に驚きなのですが、これらすべてを部活動と両立させていたのです。
「部活はサッカー部で副キャプテンをしました」
マスゲーム、サッカー部の副キャプテン、そしてさらに驚くことに、マックでアルバイトまでしていました。
6. 経済的自立への意識
ここが私が最も感心した点です。
そして保護者の皆さんにもぜひ参考にしていただきたい部分でもあります。
「やっぱりその海外の大学に行くならお金がかかるので、稼ぐに越したことはないと思ってやってるんですけど、貯めてるとかじゃなくて、使ってるんですけど、その分親に負担は、高校の間、親に経済的な負担は普通の人に比べたら、もうとてつもなくかけてないと思うので、その分、大学でお金がかかる分、高校は安く済まそうという感じです」
月に3万円程度を稼いで、「部活の服とか文房具とかは自分で、靴とか服とかは買ってます」とのこと。
高校1年の夏からアルバイトを始め、将来を見据えて経済的にも自立しようとする姿勢には本当に感心させられます。
「シフトを1週間ごとに出せるんで、テストの時は、すいませんちょっとテストなんで丸々休みでとかもできて、夏休みとかはもうバンバン入れるんで結構偏るんですけど、平均したら3万円台ぐらい」
個人的にすごいと思うのは、そうした話をきちんと実行していることですよね。
多くの高校生が「将来のために何かしたい」と言いながらも実際には行動に移せない中で、K君は自分で考えた計画を着実に実行しています。
保護者の皆さんにお伝えしたいのは、こうした自立心は一朝一夕に身につくものではないということです。
K君の場合、中学時代から自分に必要な学習環境を見極める力、高校選択での戦略的思考、そして高校生活での実行力と、段階的に成長していることがわかります。
次回は、K君の驚異的な英語力の秘密について詳しくお伺いします。
実は彼の語学力の基盤は、特殊な家庭環境にあったのです。
今回お話しした「自立心」がどのような土台の上に築かれているのか、その全貌が明らかになります。
附属高校という自由な環境で、K君がいかに自分らしく成長していったか、そして何より言ったことを実行に移す力の素晴らしさがよくわかる回でした。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


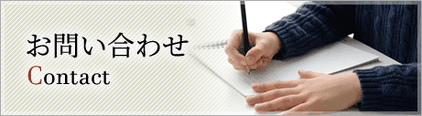
コメントをお書きください