目次
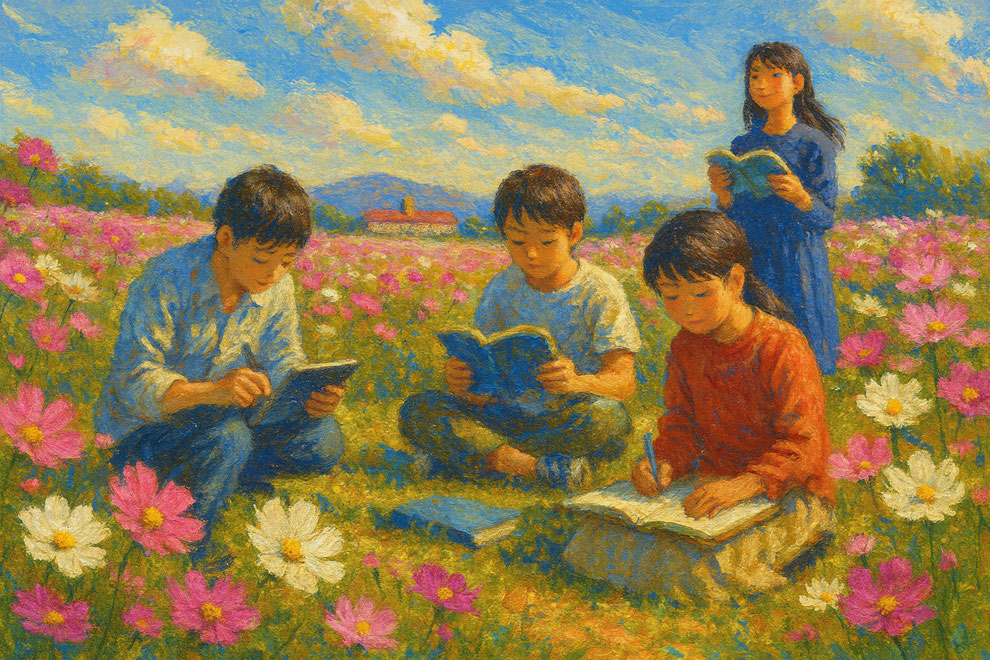
1. 漫画「教育虐待」第3巻を読んで
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
私が定期的に購読している「教育虐待」という漫画の第3巻が発売されました。
今回の内容は、私立中高一貫校で起きた悲劇的な事件をテーマにしたルポルタージュでした。
何年か前に実際にあった生徒の飛び降り自殺、そしてその巻き添えで犠牲になった生徒の事件を扱った重いテーマです。
この第3巻では、他にもさまざまな教育虐待を受けて育った子供たちのその後の話が描かれています。
せっかく難関大学に進んだのにホストにはまってしまい、犯罪に手を染めてしまった女性の話や、勉強はできるけれどもただそれだけだと思い込んでしまう有名大学の男性の話など、教育虐待の深刻な後遺症を浮き彫りにする内容でした。
この漫画を読みながら、改めて教育について深く考えさせられました。
2. 教育虐待はなぜ起きてしまうのか
教育虐待というのは、本当に親御さんの子供を思う気持ちから生まれてしまうものだと思うのです。
しかし、漫画に描かれていた状況を見ていると、基本的に子供の学力や進学先が「親の作品」であるという感覚を持ってしまったときに悲劇が起きるのではないでしょうか。
漫画「はじめの一歩」にも書かれていたと記憶していますが(笑)、ボクサーがトレーナーの作品であるように、お子さんが親御さんにとっての作品という感覚を持ってしまうと、そこから大きく道を間違えてしまうのだと感じました。
子供は親の所有物でも作品でもありません。一人の独立した人格を持った存在なのです。
子供の学力というのは、もちろん家庭環境や親御さんの学力、そして先天的な能力、育ってからの環境など、様々な要因から成り立っています。
その中に親御さんの教育という項目も確かにあるとは思いますが、だからといって完全に子供の学力や成績をコントロールできるわけではないのですよね。
結局、どれぐらい子供に裁量権を与えて、子供の自由を認めるのかということがとても大事になるのではないでしょうか。
3. 学習塾運営で見えてきた「自主性」の重要性
特に中学生以上の子が多い学習塾を運営していると、結局のところ自分の意思で、自由を与えられたときに自分の意思で勉強できるようになったときに、成績というのは大きく伸びると感じています。
その時に大切なのは、自由を与えられたときに動き出すだけのエネルギー、前向きなマインドが育っていることです。
これがなければ、いくら自由を与えても子供は動き出せません。
逆に、このエネルギーがあれば、中学校に入ってからいくらでも伸ばしていけるというのが私の実感です。
ずっとお伝えしていますが、それを大事にするからこそ、Move3年間で大幅な成績アップを果たしているのです。
4. 小学生時代に本当に大切なこと
小学生の時は、中学受験をしないのであれば、計算力と語彙力だけは基礎力として身につけておくと、中学校に入ってから伸びやすくなります。
しかし、計算力や語彙力以上に大切なのは、子供の自分で前向きに取り組もうとするエネルギーです。これを蓄えていただけたらと思います。
そのために何をしたらいいのかというと、基本的に子供には元気に遊んでもらって、過度にコントロールをしないということです。
もちろん放任すればいいという話ではありません。
ある程度の倫理観や人格形成はぜひきちんとやっていただきたいところです。
子供が元気に、自分の力で前向きに取り組めるだけの勉強にしろ何にしろ、そのエネルギーを蓄えてもらえるような小学校時代を送ってもらえたら、中学校に入ってからいくらでも伸ばしていける。
そんなふうに私は感じています。
参考にしていただけたら嬉しいです。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


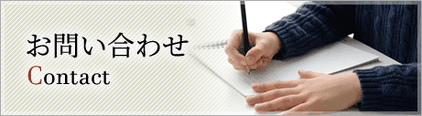
コメントをお書きください