目次
1. この間の日曜日の夜、素晴らしい対談をさせていただきました
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今日はこの間の日曜日の夜に行った、北里大学の小林先生との対談の様子をお話ししようと思います。全部で5回に分けてブログで、少しずつお話ししていこうと思います。
すごく面白かったんですね、この対談して。小林先生は哲学・倫理学がご専門で、医療系の学生さんに生命倫理学を教えていらっしゃる素晴らしい先生です。今回は先生の新刊『ゆれる時代の生命倫理』について、たっぷりとお話を聞かせていただきました。正直言うと、ファシリテーターとして本当に十分なことができたかっていうのは、私もまだ自信がないんですけど、私個人としてはめちゃくちゃ楽しかったので、その楽しかった様子を、面白いとかじゃなくて興味深いという意味で楽しかったんですけども、そういったことをお伝えできればと思います。
この5回シリーズでお話しする内容は、どれも本当に考えさせられるものばかりです。今回の「哲学との出会い」の話から始まって、次回は現代の技術が私たちに突きつける選択の悩みを扱う「生命倫理学」の世界へ。そして頭が良くなる薬の是非を問う「スマートドラッグ」の話、美容整形と自己肯定感の複雑な関係、最後は夢と現実の狭間で揺れる「好きなことで食べていけるか」という問題まで。どの話も、きっと皆さんの心に何かを残すと思います。5回に渡ってお付き合いください。
2. 受験勉強の合間に聞いた放送大学が人生を変えた
まず最初に、小林先生の哲学との出会いについて伺ったのですが、これがもう本当に興味深いお話でした。「先生、哲学を志されたきっかけは何だったんですか?」という私の質問に、先生はこんな風に答えてくださいました。
「始まりは高校生の時ですね。受験勉強の合間にラジオで放送大学の授業が流れてて、それで哲学関係の番組を聞いて、ちゃくちゃ面白い。これ何だろうっていうところから始まったんですよね」
この瞬間、私も思わず身を乗り出してしまいました。というのも、実は私も最近、放送大学に入学させてもらったばかりだったんです。「放送大学って、結構本格的な大学の授業ですよね」と私が言うと、先生も「そうなんですよね」と共感してくださいました。本当に、偶然の出会いが人生を変えるんですね。高校生の時にたまたま聞いたラジオが、その後の先生の人生の方向を決めてしまったわけですから。
3. 「当たり前」を疑う哲学の面白さと難解なヘーゲルとの出会い
「哲学の何に魅力を感じられたんですか?」という私の質問に、先生はこう答えてくださいました。「物事を根本から考えるとか、私たちが当たり前だと思ってることを、本当にそうなのかっていう風に疑問を持って見つめ直すとか、そういうちょっと普段の日常生活と違った視点から自分とか世の中を見ることができるっていうのが、すごく新鮮だったんです」
「へえ、なるほど」と私も思わず相槌を打ちました。確かに、私たちって普段、当たり前だと思っていることを疑うことって、あまりありませんよね。そして、大学院でヘーゲルを専攻されたきっかけにも、とても印象的なエピソードがありました。ヘーゲルというのは19世紀ドイツの哲学者で、その著作は非常に難解で有名なんです。哲学を学ぶ人でも「ヘーゲルは難しい」と言われるほどなんですね。
「指導教官になる方の授業に出たことで、そこでヘーゲルの論理学の授業をされてたんですね。その時、あれほど難しいヘーゲルの論理学の思弁的なテキストが絵本のように読めるっていうすごい体験をさせてもらったんです」「へえ!」私も思わず驚いてしまいました。「抽象的な言葉を、具体的なイメージにして思い描かせるっていうことにとても秀でた方だったんで、ものすごく哲学が楽しかったんですね」
この話を聞いて、私は改めて教育の奥深さを感じました。どんなに難しい内容でも、伝え方次第で相手の心に響くんですね。
4. 実際に様々な専門家の話を聞く機会を作っています
この小林先生のお話を通して改めて思ったのは、「出会い」の大切さです。高校時代の放送大学のラジオとの出会い、そして大学院での素晴らしい指導教官との出会い。偶然のような出会いが、その人の人生を大きく変えていくんですね。実は対談中にも、視聴者の方から「哲学に初めて大学で触れて、かぶりつきで聞いてました。私と同じです」というコメントをいただきました。小林先生も「同じですね。面白いですよね」と共感されていました。
だからこそ、私たちも実際に様々な専門家の方をお招きして、生徒たちや保護者の方々にお話を聞いていただく機会を作っています。今度の日曜日には広島工業大学の大谷教授をお招きして、AI時代を生き抜く力についてお話しいただく予定です。このように、いろんな人のいろんな話を聞くっていうことを、私たちはすごく大事にしています。小林先生のように「これ何だろう?面白い!」と思える瞬間が、きっと子供たちにもあるはずです。学びとの素敵な出会いは、思わぬところにあるものです。それが放送大学のラジオかもしれないし、図書館の一冊の本かもしれない。そして、私たちが企画するような講演会かもしれません。
5. アンテナを立てることの大切さ
そして、アンテナを立てるということもぜひ知っておいて欲しいなと思います。小林先生が放送大学の授業を聞いていたというところから話が始まったんですけれども、それが本当に放送大学の授業でも聞いてみようって思ってしまうところから、やっぱり学問の楽しさとか出会いっていうのが伝わってくるんだなっていうのは、この話を考えるだけでも皆さんにお伝えできるんじゃないかなと思います。
アンテナを立てるという意味で、この対談自体がその機能を果たしてくれるとすごく嬉しいなと思います。大切なのは、いつでもアンテナを張って、好奇心を持ち続けることなのです。
ところで、次回は小林先生の専門である「生命倫理学」の世界に足を踏み入れます。技術の進歩で私たちの選択肢が広がった分、逆に「どう選んだらいいのか分からない」という新しい悩みも生まれているそうなんです。命の始まりから終わりまで、現代の私たちが直面する8つのシチュエーションを通して、この複雑な時代をどう生きていけばいいのか、一緒に考えてみませんか?


進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。





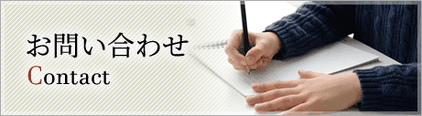
コメントをお書きください