目次
1. シリーズ第2回、生命倫理学の世界へ
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今回は、北里大学の小林亜津子先生との対談シリーズ、第2回をお届けします。前回は小林先生の哲学との出会いについてお話ししました。高校時代の放送大学のラジオが人生を変えたという、本当に素敵なエピソードでしたね。
この対談シリーズでは全5回に渡って、小林先生の新刊『ゆれる時代の生命倫理』について、たっぷりとお話を伺っていきます。第2回の今回は、小林先生の専門である「生命倫理学」について、深く掘り下げていきたいと思います。
生命倫理学って、言葉だけ聞くと何だか難しそうですよね。実は私も、小林先生の本を読むまでは、正直なところ難しそうだなと思っていました。専門的で、自分には縁遠い学問なんじゃないかって。でも、本を読み、そして小林先生のお話を聞いていくうちに、これは本当に私たち一人一人に関わる、とても身近で大切な学問なんだということが分かってきたんです。
2. 生命倫理学とは何を扱う学問なのか
「先生、生命倫理学っていうのは、どういう学問なんですか?」という私の質問に、小林先生はこう答えてくださいました。
「主に人間の生命とか、先端医療技術に関する倫理問題を扱う分野ですね。新しい技術ができた時に、でもこれ使っていいのかどうかとか、誰がそれにアクセスできるかとか、あるいはその技術の配分、かなり高額だった場合に誰に使ってもらうかとか、色々なことがあります」
「なるほど」と私も頷きました。確かに、医療技術って日々進歩していますよね。でも、技術ができたからといって、すぐに「じゃあ使いましょう」とはいかない問題があるんです。
先生は続けてこうおっしゃいました。「延命医療とかも進歩して、命の終わりをどう決めたらいいのか。恣意的に人間の死の時期っていうのをある程度コントロールできるようになってきてますよね。食べられなくなったら胃ろうとか経管栄養とかっていうように、言葉は良くないかもしれませんけど、命を長らえさせるっていうことはできるようになったんだけれども、その時に果たしてそれをするかどうか、していいのかどうかっていうことですよね」
この話を聞いて、私は改めて生命倫理学の重要性を感じました。技術は進歩する。でも、その技術をどう使うか、使うべきか使わないべきか。これは本当に難しい問題ですよね。
3. 「自己決定権」という言葉が生まれた時代
私は先生にこう尋ねました。「これってあれですよね、今から20、30年くらい前に、自己決定権っていう言葉が言われるようになって、本当にいろんな方の、もう寿命を迎えられるような方たちの医療として、チューブを入れて延命することはできるけど、果たしてそれは本当に人として正しい医療のあり方か、みたいなところをまさにピンポイントで追求していくようなのが生命倫理という風に捉えても大丈夫ですか?」
「まさにそうですね」と先生も答えてくださいました。
そして、命の終わりだけではなく、命の始まりについても大きな問題があるんです。「体外受精とか代理出産とか、あと精子バンクとかですね。そういう風にその、どこまで命を人為的に操作していいのかとか、そしてそういった人工生殖で生まれてきた子供たちが何を思うのかとかですよね」
4. 人生のライフサイクルに沿った8つの問題
小林先生の新刊『ゆれる時代の生命倫理』は、本当に興味深い構成になっています。全部で8章あるんですが、この8章が私たちのライフサイクルに沿って問題を並べているんですね。
「出版社の編集者さんと話し合った時に、私たちのライフサイクルに沿って起こる問題を並べようということになったんです。第1章が学生時代のスマートドラッグの問題で、そこからだんだんお年頃になって自分の容姿を気にし始める美容整形の問題。さらに家庭を持つかどうかとか、子供ができた時の出生前診断の問題とか。で、最後は自分の死とか命の終わり、そして介護のところでケアロボットの問題まで」
「へえ」と私も感心してしまいました。普通の生命倫理学入門の本だと、第1章や第2章のスマートドラッグやエンハンスメント、美容整形の問題ってあまり出てこないそうなんです。第3章から第6章あたりが定番で、第8章のケアロボットは最近になって追加された新しいテーマなんだとか。
「現代っていうのは技術の進歩が加わって、問題がさらに複雑化してるんですよね。かつてだったらスマートドラッグなんてなかったんで、勉強ができないっていうのはもうそこで終わりだったのが、スマートドラッグで挽回できる可能性があるとか。あるいは美容整形も、持って生まれた顔でそのままだったのが、変えられるっていう風になった場合に、個人の自由でそれをどこまで追求していいのかって問題が出てくる」
まさにそうなんですよね。新たな技術が登場して、出生前診断もそうですけど、選択の幅が広がったおかげで、逆にどう選んだらいいのかっていう、選択の自由が悩みになってしまったんです。
5. 技術の進歩が生む「選択の悩み」
この話を聞いていて、私は本当に考えさせられました。技術が進歩するっていうのは、確かに素晴らしいことです。でも、それによって私たちの選択肢が増えた分、「どれを選ぶのが正しいのか」という新しい悩みも生まれてしまったんですね。
小林先生の本は、そういう問題に遭遇した時に、「こういう視点から整理してみたらどうですか」っていう議論の整理をしてくれる本なんです。正解を教えてくれるわけじゃない。でも、考えるための道筋を示してくれる。これって、本当に大切なことだと思うんです。
最初は難しそうだなと思っていた生命倫理学ですが、小林先生の本を読み、お話を聞いて、これは本当に私たち全員が考えるべき問題なんだと実感しました。
次回の第3回では、この8章の中から第1章の「スマートドラッグ」について詳しくお話しします。頭が良くなる薬があったら、あなたは使いますか?そして、それを使うことは「ずるい」ことなのでしょうか?この問題、実は中学生から質問を受けたことがあると小林先生はおっしゃっていました。子供たちにとっても切実な、そして本質的な問いなんです。どうぞお楽しみに!


進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。





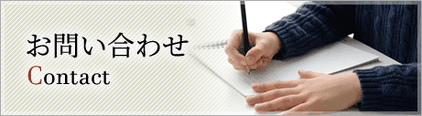
コメントをお書きください