目次
1. 頭が良くなる薬、使ってもいいの?
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今回は、北里大学の小林亜津子先生との対談シリーズ、第3回をお届けします。
このシリーズは全5回構成で、小林先生が出版された『ゆれる時代の生命倫理』という本をもとに、子どもたちや保護者の方々に生命倫理という学問を知っていただくことを目的としています。第1回では小林先生がどのように哲学と出会い、生命倫理学の道に進まれたのかをお話しいただきました。第2回では生命倫理学とはどんな学問なのか、命の始まりと終わりに関わる現代の問題について触れました。
そして今回、第3回のテーマは「スマートドラッグ」です。続く第4回では美容整形と自己肯定感、第5回では好きなことで食べていけるかという学問の道の現実について、小林先生の経験を交えてお話しいただく予定です。
スマートドラッグ。皆さん、聞いたことがありますか?
私は正直、小林先生の本を読むまで、あまり馴染みがありませんでした。でも、小林先生によると、中学生くらいから密かに問題になっているテーマなのだそうです。
スマートドラッグとは、簡単に言えば、人間の認知能力をアップさせる薬のことです。脳の認知能力、つまり集中力や記憶力を高めて、勉強のパフォーマンスを上げる。そういう薬があるんですね。
もともとはADHDなど発達障害の方のための薬だったのですが、それを健常者が使っても、ある程度の能力アップが見込めるということで、一部で使われているのだそうです。
さて、これを使って成績を上げることは、是か非か。今日はこのテーマについて、小林先生のお話を交えながら考えていきたいと思います。
2. 「ずるい」と言い切れない理由
スマートドラッグを使って勉強の成績を上げる。これを聞いて、多くの方は「それはずるいでしょ」と思われるのではないでしょうか。私も最初はそう思いました。
でも、小林先生の著書にはこう書かれています。
「スマートドラッグを使うことは、私たちが単純に考えるほど、ずるいことではないかもしれない。世の中には、生まれながらにして、ずば抜けた認知能力を持つ人たちがいる。彼ら彼女らは、学校の試験の成績だって良いだろう。そのような能力に関して、人間は生まれながらに不平等である」
そうなんですよね。そもそも、生まれながらにして能力差があるわけです。
頭の良い子は、勉強しなくてもテストで良い点が取れる。でも、どんなに頑張っても、なかなか点数が上がらない子もいる。この不公平さは、確かにあります。
だとしたら、その能力差を埋めるためにスマートドラッグを使ってもいいんじゃないか。そういう意見も、理屈としては成り立つわけです。
実際、小林先生の学生さんの中には、こんな意見を言う人もいたそうです。
「じゃあ、自分は、じゃあみんなが、スマートドラッグを使い出したとしたら、自分は同調圧力に負けて使ってしまいそうです。自分だけが使わないことで、不利になってしまうことは受け入れがたいです」
これ、本当にリアルな意見だと思います。みんなが使い始めたら、自分も使わざるを得なくなる。そういう状況は、十分に想像できます。
3. 安全性・公平性・主体性の問題
では、スマートドラッグの何が問題なのか。小林先生は3つの点を挙げられています。
1つ目は安全性。薬である以上、副作用や依存性の問題があります。これは当然、大きな問題です。
2つ目は公平性。ただし、これについては先ほど述べたように、難しい面があります。
小林先生はこうおっしゃっていました。
「高額な予備校とか、カリスマ家庭教師とか、経済的余裕のある人はそういったものを使って、で、学力を上げることができるって、いうのがあって、すでに不公平っていうのはあるんじゃないかって言う」
これ、以前に中学生から質問を受けたことがあるそうで、小林先生も「なるほど」と思われたそうです。
塾の先生としては、ちょっと耳が痛い話ですが、確かにそういう面はあります。経済的な余裕のある家庭の子は、良い教育環境を得やすい。この不公平さは、既に存在しているわけです。
そして3つ目が、主体性の問題。これが一番重要だと、私は思います。
4. 本当の自分の力じゃない?
小林先生はこう指摘されています。
「例えば、薬を使ってパフォーマンスが上がって、で、試験でいい成績を掴んだって場合、それが本当に自分の自信になるのかどうかっていうことですよね」
薬のおかげで点数が上がった。でも、それは本当に自分の実力なのか。
薬を使って結果を出したという思いが、どこかにあると、後々、その自分自身の実力じゃなかったっていうことが、なんか自分自身の負い目というか、自信のなさっていうところに繋がってくるんじゃないか。本当の自分じゃないとか、自分の力じゃないみたいな感覚です。
そして、小林先生の著書には、こう書かれています。
「結局、この心の底から湧き出てくるような知的好奇心、もっと知りたいという感覚を味わったり、何かに熱中して学ぶことの楽しさ、勉強の面白さを実感したりすることなく、大事な学生生活を終えてしまうということは、本当にもったいないことだと思ってしまう」
これなんですよね。勉強って、本来は楽しいものなんです。
5. 勉強する意味、学ぶことの楽しさ
小林先生は対談の中で、こんな素敵なことをおっしゃっていました。
「受験勉強自体が楽しいかって言われて、って感じではあるんですけど、だからその間に放送大学を聞いたりとかして、ちょっとなんか、気晴らしをしたりとかして、て大学入ったらこういったことが学べるんだっていうのを、こうモチベーションにして受験勉強してたっていうのがあるんで」
そして、「もしですね、何のために勉強するんですかって私が聞かれたとしたら、この人生の見晴らしを良くするためって答えると思うんですよね」とも。
知識がつくと、世界の見え方が変わる。これ、本当にそうなんです。
私も高3の春まで全然勉強してなかったんですが、そこから受験勉強を始めたきっかけが、英語の文法の面白さに気づいた瞬間だったんです。「あ、こういうことだったんだ!」と思った時に、勉強が進んだ。
なんかきっかけがあって、「あ、これって面白いんだ」と思った時に、見えてくる世界が変わる。その経験があるかどうかって、すごく大きいと思うんです。
実際、視聴者からもこんなコメントをいただきました。ADHDでスマートドラッグに該当する処方薬を内服されている方のお子さんの話です。
「彼曰く、集中力は高まるけれども、本来なら湧き出る閃きはなくなるとのことです。つまりスマートドラッグにより得られる効果ばかり望まれる社会構造に疑問を感じます」
これ、本当に深い指摘だと思います。
集中力は高まるかもしれない。でも、「あ、そうか!」という閃き、発見の喜び、学ぶことの楽しさ。そういうものが失われてしまう可能性があるわけです。
6. 私たちが子どもたちに伝えたいこと
スマートドラッグの問題は、実は「勉強とは何か」「学ぶとは何か」という本質的な問いに繋がっているのだと思います。
成績を上げることだけが目的なら、スマートドラッグを使えばいいかもしれません。でも、それで本当にいいのでしょうか。
私たち大人が、子どもたちに伝えなければならないのは、学ぶことの本当の楽しさ、知ることの喜びではないでしょうか。
今まで分からなかったことが分かった時の、あの「そういうことか!」という感動。知識が繋がって、世界の見え方が変わる瞬間。そういう体験を、子どもたちにしてほしいと、心から思います。
スマートドラッグについて、簡単な答えはありません。安全性が確立されて、誰でも使えるようになったら、使ってもいいのか。それとも、やはり使うべきではないのか。
でも、少なくとも言えることは、薬に頼って成績を上げることよりも、学ぶことそのものの楽しさを知ることの方が、その子の人生にとって、ずっと価値があるということです。
小林先生の著書『ゆれる時代の生命倫理』には、こうした問題が、さらに深く、そして分かりやすく書かれています。ぜひ手に取って、お子さんと一緒に考えてみてください。
次回、第4回は「美容整形から見えてくる自己肯定感の問題」をテーマにお届けします。


進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。





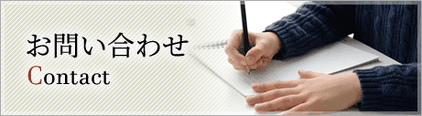
コメントをお書きください