目次
1. 「外見の問題」では片付けられない
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今回は、北里大学の小林亜津子先生との対談シリーズ、第4回をお届けします。
この対談シリーズは全5回構成で、小林先生が出版された『ゆれる時代の生命倫理』という本をもとに、子どもたちや保護者の方々に生命倫理という学問を知っていただくことを目的としています。第1回では小林先生がどのように哲学と出会い、生命倫理学の道に進まれたのかをお話しいただきました。第2回では生命倫理学とはどんな学問なのか、命の始まりと終わりに関わる現代の問題について触れました。第3回ではスマートドラッグを題材に、「勉強する意味」や「学ぶことの本質的な喜び」について考えました。
そして今回、第4回のテーマは「美容整形」です。続く第5回では、「好きなことで食べていけるか?」という学問の道の現実について、小林先生ご自身の経験を交えてお話しいただく予定です。
美容整形と聞くと、「外見を良くするための施術でしょ?」と思われる方が多いかもしれません。私も正直、最初はそう思っていました。でも、小林先生のお話を伺って、視聴者の皆さんからいただいたコメントを読んで、この問題は単純に外見の話ではないのだと気づかされたのです。
むしろこれは、自己肯定感の問題であり、他者との関係性の問題であり、そして親子関係にも関わる深いテーマなのです。特に思春期の子どもたちにとっては、容姿のコンプレックスは本当に大きな問題ですよね。
2. 心を救う治療?それとも自己否定の始まり?
小林先生が著書の中で書かれている言葉が、私にとってはとても印象的でした。
「美容整形自体は医療ではない。しかし、それによって本人が精神的苦痛から解放されるのなら、それは精神科という医療にもなりうる」
この言葉、深いですよね。
身体的に見れば、美容整形は病気の治療ではありません。むしろ健康な体にメスを入れる行為です。でも、容姿にコンプレックスを抱いていて、そのことで日常生活がうまくいかないと感じている人がいる。そういう人が、プチ整形をすることでカラッと明るくなることもあるのだそうです。
小林先生は、これを「救済治療」と表現されました。心を救う治療、という意味ですね。
実際、視聴者の佐藤さんからこんなコメントをいただきました。「思春期は容姿のコンプレックスはかなり大きい問題でした。親から性格美人になれと言われ、精神性を求める考えに反発もしてきました。年齢を重ねると親の言っていたことが分かってきました」
佐藤さんのように、思春期には容姿のコンプレックスが本当に大きな問題だったけれど、年齢を重ねるとその見方が変わってくる、ということもあるわけです。でも、思春期のその時期には、本当に辛いんですよね。
だからこそ、美容整形を単純に否定することはできない。そう思うのです。
3. 「可愛い」って、誰が決めたの?
とは言え、小林先生はこうも指摘されています。
「美容整形は何よりも自分の心地よさや自己満足のためになされるものではあるが、その背後には常に同性異性に評価されたい、若く見られたいからなど、他者の意識がつきまとっている」
これ、本当にその通りだなと思いました。
自分が整形したいと思う時、それは本当に自分自身のためだけなのか。それとも、他者の目線を自分の中に内面化して、「こうじゃなくちゃいけない」と思い込んでいるのではないか。
例えば、ふたえ。女の子にとってふたえが可愛いという価値観は、どこから来ているのでしょうか。小林先生は、これは社会的にすり込まれた美の基準なのではないか、とおっしゃっていました。
視聴者からも「Instagram、TikTokなど若い人向けのSNSはまさにビジュアル第一になっていると思う。そこからの同調圧力のようなものもありそう」というコメントをいただきました。まさにその通りですよね。
今の時代、SNSでキラキラした世界を見せられて、容姿が優れている人ばかりが目に入ってくる。それと自分を比較して、「自分もああならなくちゃいけない」と思ってしまう。これは個人の自由な選択のように見えて、実は社会的な圧力の中での選択なのかもしれません。
小林先生は「美容整形って、個人がこうしたいって思うことという面だけではなくて、結構社会的な行為であって、他者の目線を自分の中に内面化して、ここはこうじゃなくちゃいけないという風に思い込んでいる」とおっしゃっていました。
この指摘は、本当に重要だと思います。
4. 「お父さんに似てる」その顔を変えたいと言われたら
さらに、小林先生が指摘されたのは、体の外見が自分のアイデンティティと繋がっているということです。
例えば、自分は東洋人である、とか、自分は誰それの子どもである、とか。親と容姿が似ているということは、親との血の繋がりを表現している媒体でもあるわけです。
対談の中で、小林先生がこんなエピソードを紹介されました。ある若い女性が、自分の顔立ちにすごくコンプレックスを持っていて、テレビでそのことを語っていた。その時、カメラが彼女を映した後、お父さんを映したそうです。お父さんそっくりだったのですね。お父さんは何も言わずに黙っていた。その光景が、小林先生の記憶に残っているとおっしゃっていました。
親目線から見ると、子どもが自分と似ている容姿を変えたいと言われるのは、結構ショックなのではないか。小林先生の学生さんの中にも、「親に申し訳ない気がするから、自分は整形を受けないでおこう」と考える人がいるそうです。
小林先生の著書の中には、こう書かれています。
「整形で容姿を変えてしまうことで、親が自分の容姿や、場合によっては親子関係を否定される気持ちになってしまうのではないか」
私も今、中学3年生の息子がいます。息子は私にそっくりだとよく言われます。私は息子が可愛いし、大好きです。でも、もし息子が何らかの形でコンプレックスを抱いて、「変えたい」と言った時、私はどう思うだろう。そう考えると、この問題の深さが分かる気がしました。
5. 正解はない、けれど伝えたいこと
そして、小林先生が最も深く問いかけているのは、この点です。
「究極的には、本人の真の自己肯定感に繋がることのない、個々人の自由な自己否定に他ならないという見方もできるのではないだろうか」
美容整形は、ある意味で自分を変えるということです。今の自分ではダメだ、という思いがあるのではないか。本人は自分で自由に自分の容姿を変えて、綺麗になりたいと思っているように見えても、実はそこには絶えず「今の自分ではダメだ」という否定が積み重ねられているのではないか。
小林先生は、「今の自分のありのままを、そしてそれは親との繋がりも含めて、受け入れることができるといいですよね」とおっしゃっていました。
もちろん、「それは綺麗な人だから言えることよ」という意見もあるでしょう。実際、私もそう思いました。でも、小林先生は「誰しも多分コンプレックスってのはあると思うんですよ」とおっしゃって、ご自身も「もうちょっと身長が高ければよかったな」とずっと思っていたと打ち明けてくださいました。
私も身長175センチ、体重90キロ超えの体型で、これはこれでコンプレックスがあります。誰しも、何かしらのコンプレックスはあるものですよね。
視聴者の佐藤さんも、「地域や時代で美に対する基準が違うので、若い時にこだわっていたことが今では懐かしいです」とコメントしてくださいました。時間が経てば、見方が変わることもある。でも、思春期の真っ只中にいる子どもたちにとっては、それは遠い未来の話かもしれません。
だからこそ、この問題に簡単な正解はないのだと思います。美容整形を完全に否定することもできないし、無条件に肯定することもできない。
けれど、私は教育者として、そして一人の親として、子どもたちに伝えたいことがあります。それは、自分自身を全て受け入れることの大切さです。
容姿も、性格も、生まれ育った環境も、親から受け継いだものも、全部ひっくるめて「自分」なのだということ。今の自分に満足できなくても、それでも今の自分を否定せずに、「これが自分なんだ」と受け入れることから始めてほしい。そう思うのです。
もちろん、それは簡単なことではありません。私自身も日々、自分の至らなさと向き合いながら生きています。でも、子どもたちが少しでも自分を肯定できるような環境を作っていくこと、それが私たち大人の役割なのではないでしょうか。
小林先生の著書『ゆれる時代の生命倫理』には、こうした問題がさらに詳しく、そして深く書かれています。ぜひ手に取って、読んでいただけたらと思います。
次回、第5回は「好きなことで食べていけるか?学問の道の現実」というテーマでお届けします。哲学を専攻することの現実、そして研究者の道について、小林先生の経験を交えながらお話しします。


進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。





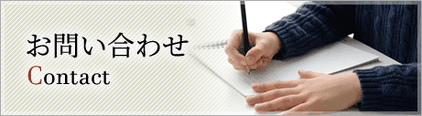
コメントをお書きください