目次
1. 「哲学で食べていけるか?」考えたことありませんでした
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今回は、北里大学の小林亜津子先生との対談シリーズ、第5回・最終回をお届けします。
このシリーズは全5回構成で、小林先生が出版された『ゆれる時代の生命倫理』という本をもとに、生命倫理という学問を皆さんに知っていただくことを目的としてきました。第1回では小林先生の哲学との出会い、第2回では生命倫理学という学問の本質、第3回ではスマートドラッグと勉強の意味、第4回では美容整形と自己肯定感について考えてきました。
そして最終回となる今回のテーマは、「好きなことで食べていけるか?学問の道の現実」です。
ライブ配信中、視聴者の方からこんな質問をいただきました。「息子は数学が好きですが、数学で食えるビジョンが見えないと言っています。大学進学時、哲学を専攻するにあたり『食っていけるか』ということは考えられましたか?」
この質問に対する小林先生の答えが、私には本当に印象的でした。
「いや、食っていけるかどうかも考えてなかったんで、それがね、後々、博士課程後期とかになっても潰しが効かない状況になった時に、あああ、そう言えばと。数学選択した、という感じですかね」
高校時代にラジオで放送大学の哲学の授業を聞いて、「これ、めちゃくちゃ面白い!」と思った。そのまま哲学の道に進んだ。食べていけるかどうかなんて、考えもしなかった。
この純粋さが、私にはとても素敵に感じられました。でも同時に、その後の現実の厳しさも、小林先生は率直に語ってくださったのです。
2. 博士号を取っても、10年かかった就職
小林先生は京都大学の大学院で哲学を専攻されました。博士課程は通常3年間ですが、博士号を取るのに3年では間に合わなかったそうです。プラス2年。さらに、哲学の場合、博士号を取ったからといってすぐに就職があるわけではありません。
「しばらく、京都で非常勤をかけ持ちしながらやっていた時期もあるんですね」
小林先生はこうおっしゃっていました。
大学院に入って、博士号は取って哲学博士となったけれども、大学の職につくまでには10年くらいかかった。これが現実です。
さらに、小林先生はこう続けられました。
「今、日本の大学でもポストが削られていって、哲学の教員がやめると、そのあと、補充でそのポスト取らなかったりして、どんどんその、人文科学っていうのは、縮小される傾向にあるんで、ますます、哲学とかの、もう食べていくの難しくなると思うんですけれども」
少子化で大学がなくなっていく。必然的に、研究者や教員職のポストが減っていく。これは本当に大きな問題です。
では、小林先生はどうやって今の職を得られたのか。それは、生命倫理という分野との出会いがあったからです。
3. 生命倫理との出会いが道を開いた
小林先生が生命倫理に出会ったのは、博士課程後期に入ってからでした。
「やっぱりその、なんですね、その実際に今、起こってる現代のその問題に対しても何かしら哲学の観点からこうアプローチできないだろうかっていう問題意識があって、そこからでしたかね」
ヘーゲルだけをやっていたら、多分今でも大学の職につけていなかったかもしれない。そう小林先生は率直におっしゃっていました。
ちょうどその頃、医療系の大学で生命倫理の教育が重視されるようになり、倫理学のポストが作られる動きが起こったのだそうです。小林先生は、その最後に滑り込んだ形だとおっしゃっていました。
ヘーゲルという古典的な哲学と、生命倫理という現代的な問題。その両方を学んだことが、小林先生の道を開いたわけです。
でも、これは運が良かったケースでもあります。すべての人がこうなるわけではない。それも現実です。
4. 「絶対やめろとは言わないけど、君の責任だよ」
ライブ配信の中で、小林先生がこうおっしゃっていました。
「学生からの質問で一番困るのがこういう感じの質問で、学者になりたいんですけど、どうすればいいですかと、大学院行ったらなれますかとか、大学院ってドクターまで行って研究者になりたいんですとかっていう相談を受けるのは結構困る」
若い人の夢を潰したくはない。でも、現実がどれだけシビアかも伝えなければならない。
そんな時、小林先生は恩師から言われた言葉をそのまま学生に伝えるのだそうです。
「私が自分の恩師にその大学院って研究者になりたいって言った時に言われた言葉をそのまま、そのバトン、言葉のバトンを渡すみたいにしてるんですよね」
その言葉とは、こうです。
「絶対やめろとは言わないよ。でも、現実的にそれでは食べてけません。ただ、やりたいならやればいいんじゃん。でも、覚悟を決めて、君の責任だよ」
そして最後に、こう付け加えるのだそうです。
「私があれでですね、じゃあ、こう、やりたいことああって追求してって、もちろん苦労した時代もあったけど、いろんなご縁があって、大学の教授職に、しっかりと活躍されてる方もいらっしゃる」
現実は厳しい。でも、可能性はゼロではない。そして、自分の人生は自分で決める。その覚悟を持ってほしい。そういうメッセージなのだと思います。
5. 私も「院生崩れ」でした
実は、私自身も似たような経験をしています。
私は大学院でドイツ経済史、ヨーロッパの経済史を研究していました。博士課程後期まで進みました。その頃は、本当に面白かったんです。今でも面白いと思っています。
でも、ある時期に現実が見えました。この道では食べていけない、と。
それで、私は塾の先生という道を選びました。いわゆる「院生崩れ」というやつですね。
視聴者のゆゆラボさんからも、こんなコメントをいただきました。「心理学科でした。つぶしが聞かないからと、学校の先生になりましたが、結局やめて、カウンセラーをしています。人生の道っておもしろいです」
そうなんです。人生の道って、本当に面白いんですよね。
私は研究者にはなれませんでしたが、今、塾で子どもたちに教えることができています。経済史で学んだこと、大学院で培った思考力は、今の仕事に確実に生きています。そして何より、学ぶことの楽しさを子どもたちに伝えることができている。
ゆゆラボさんも、心理学を学んだことが、今のカウンセラーという仕事に繋がっています。
回り道に見えるかもしれません。でも、その道があったからこそ、今の自分がある。そう思えるのです。
6. それでも、好きなことを追求する意味
視聴者の銀杏さんから「純粋に学びを探求されたという先生、素敵です。ご回答ありがとうございます」というコメントをいただきました。
本当にそうだと思います。小林先生が高校時代に放送大学のラジオで哲学に出会い、純粋に「面白い!」と思って、その道に進んだこと。食べていけるかどうかなんて考えずに、ただ好きだから学び続けたこと。
その純粋さは、本当に素敵だと思います。
もちろん、現実を無視することはできません。食べていかなければ生きていけません。特に今の時代、大学のポストは減り続けています。研究者になる道は、本当に厳しい。
でも、だからといって、好きなことを諦める必要があるかというと、そうでもないと思うのです。
私が子どもたちに伝えたいのは、こういうことです。
好きなことを見つけてほしい。それを深く学んでほしい。そのこと自体に価値がある。たとえそれで直接食べていけなくても、その学びは必ずあなたの人生を豊かにする。そして、思わぬ形で将来に繋がっていくこともある。
数学が好きなら、数学を学んでほしい。哲学が好きなら、哲学を学んでほしい。歴史が好きなら、歴史を学んでほしい。
ただし、現実も知っておいてほしい。特に大学院、博士課程まで進むなら、その道の厳しさは理解しておく必要があります。そして最後は、自分で決める。自分の責任で決める。
小林先生の恩師の言葉は、本当に重いと思います。「絶対やめろとは言わないよ。でも、現実的にそれでは食べてけません。ただ、やりたいならやればいいんじゃん。でも、覚悟を決めて、君の責任だよ」
私も全く同じことを、進路で悩む生徒たちに伝えています。
現実を知った上で、それでもやりたいなら、やればいい。覚悟を決めて、自分の人生を生きればいい。そして、どんな道を選んだとしても、学んだことは決して無駄にはならない。
小林先生は、哲学を学び、生命倫理を学び、今こうして大学で教鞭を取りながら、一般の方々にも生命倫理を伝える活動をされています。『ゆれる時代の生命倫理』という素晴らしい本も出版されました。
回り道があったからこそ、今の小林先生がある。そう思うのです。
この対談シリーズを通じて、生命倫理という学問の深さ、そして学ぶことの意味を、少しでも皆さんに伝えることができたなら嬉しいです。
小林先生、本当にありがとうございました。そして、最後までお読みいただいた皆さん、ありがとうございました。


進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。



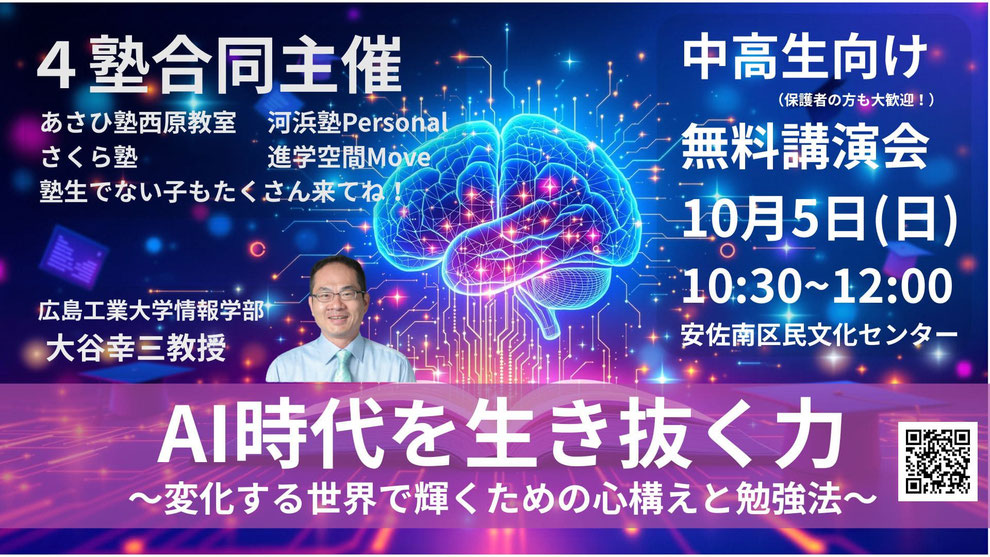

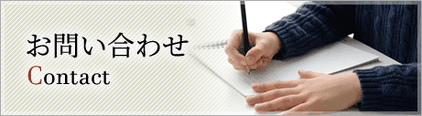
コメントをお書きください