目次

1. あるツイートから始まった疑問
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
先日、Twitter(もちろん現在のXのことです。馴染みのある表記にしています)で気になる投稿を見かけました。
中学受験をされている保護者の方のツイートで、「子どもの能力は認知能力と非認知能力に分かれ、非認知能力は大人が鍛えることができないので、認知能力つまり学力を鍛えてあげることが親の責務である」という内容でした。
最初は「少し違うかな」と感じたのですが、調べてみると、その方の言う「認知能力」と私が理解している認知能力には大きなズレがあることが分かったんです。
どうやら一部の教育業界では、認知能力を「テストで測れる数値化可能な能力」として使っているようですね。
2. 本来の認知能力とは何か
私の理解では、認知能力とは外部の世界をどのように認識し、理解するかという能力のことです。
同じ風景を見ても、人によって見えている世界は違います。
色の見え方、音の聞こえ方、匂いの感じ方も一人ひとり異なるんですね。
学習と関連して言えば、その世界をどう切り取って理解し、その中で自分がどう行動すべきかを判断する、もっと広い意味での認知に関わる能力だと考えています。
子どもが「なぜこうなるんだろう?」と疑問を持ったとき、まずはその考えを聞いてあげることから始めてみませんか。
3. 知識によって変わる世界の見方
この認知能力は、本人の持つ知識によって大きく変わります。
経済学を学んだ人は世の中を経済的な観点から見ることができ、法学を学んだ人は社会の仕組みを法的な視点で捉えます。
物理学を学んでいる人なら、物事の動きを物理的に理解するでしょう。
つまり、世の中の切り取り方は本人が持っている知識に大きく左右されるのです。
だからこそ、一つの分野に偏らず、理系・文系問わず幅広い分野に触れさせてあげたいですね。
散歩中に「この建物はなぜこんな形なんだろう?」と一緒に考えたり、料理を手伝ってもらいながら「なぜお肉に火を通すのかな?」と科学的な視点を育てることもできます。
4. 親にできること、できないこと
こうした世界の見方こそが認知能力の本質であり、これを親が直接コントロールできるものではありません。
何を学び、どのように物事を捉えるかは、子どもたち自身が経験や知識、身体能力を含めて総合的に育んでいく能力なのです。
でも私たちにできることはあります。
子どもの「なぜ?」「どうして?」という疑問を大切にし、一つの答えだけでなく「他にはどんな見方があるかな?」と一緒に考えてみる。本やニュースを見るときも「君はどう思う?」と問いかけて、子ども自身の視点を引き出してあげることが大切だと思います。
5. 本当に大切にしたい学びとは
認知能力という言葉を表面的に捉えて、外部からコントロールできると考えるのは危険です。
この能力を大切にすることには大賛成ですが、決してテストの得点を上げるための道具にしてはいけないと思うのです。
様々な経験や知識を通じて、いろんな世界の見方ができるようになり、それが深く自分の行動につながる。
そんな本当の意味での認知能力を、子どもたちには身につけてもらいたいですね。
日常の何気ない場面でも、子どもが様々な角度から物事を見る機会を作ってあげることから始めてみましょう。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


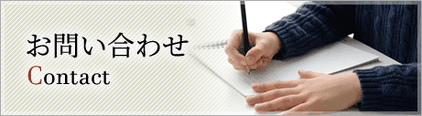
コメントをお書きください