目次

1. 中学1年生が持ってきた規則性の問題
こんにちは。進学空間Moveの宮脇です。
今日は、塾らしくある数学の問題についてお話したいと思います。
先日、ある中学1年生の子がこんな問題を質問に持ってきました。
「先生、やり方を教えてください」と。
どうでしょう、皆さんも同じような経験はありませんか?
問題はこういうものでした。
A、B、Cの文字が1つずつ書かれた3種類のカードを、A、B、B、Cが左からこの順に繰り返されるように何枚も並べていく。
カードを45枚並べるとき、45枚目に並ぶカードに書かれた文字を答えなさい、というものです。
分かっている方としては、何も難しくはありません。
規則性を考えて、45÷4=11あまり1の計算をし、あまりが1なのだから、繰り返される4枚のカードの1枚目であるAが45枚目に来ると答える問題なのです。
ほら、難しくないでしょ?
2. 「45個全部書いてみなさい」という指導
でも、ここでこのやり方を教えてはいけないのです。
驚くべきことに、そんな方法が分からなくても問題が解けるのですから。
私の指示は、「45個のアルファベット全部書いておいで」でした。
その子は、意外そうな顔をしました。
きっと計算式を教えてもらえるものと思っていたのでしょう。
でも、それでは本当の学習にならないのです。
なぜだと思いますか?
だって、これは自分で一度書いてみて、その中で法則性に気づく問題なのですから。
じゃないと、この問題の続きも絶対解けません。
文字式で表すこともできなければ、説明しなさいという問題も、無理なのです。

3. 失敗するチャンスを奪ってはいけない
このような規則性を見抜く問題によく表れることですが、「試行錯誤力」が弱い子が増えたなあと思います。
皆さんはどう感じておられるでしょうか?
昔から多いのも否めませんが、最近特にそう感じるのです。
最終的に法則が見抜けなくて、計算式が立てられないことを問題にしたいのではありません。
最終的な解法は後々にマスターしていけばいいだけです。
そのために私たち先生がいますからね。
タイミングが来たらいくらでも伝えます。
でも、それ以上に大事なことは何でしょう?
とりあえず45個のアルファベットくらいは、まず自分で書いてみることです。
全てはそこからでしょう。
書きながらあれこれ考えて、見つけた法則性を数式にしてみようとする。
もちろん失敗することもあるでしょう。
それをまたあれこれ考え直す。
この過程こそがその子の学力になるのです。
4. 小さい時から育みたい試行錯誤力
やはりなんでもかんでも、大人が先回りして子供達から「失敗するチャンスを奪う」ことは慎まないといけないですね。
大事なのは、小さい時から自分であれやこれや試して、失敗して、試して、失敗して、また試すような試行錯誤力なのです。
学力がある子というのは、こういうことにも果敢にチャレンジするものです。
答えがすぐに分からなくても、とりあえずやってみる。そして、やりながら考える。
そういう姿勢が身についているのです。
この姿勢こそが、本当の学力の源泉だと思いませんか?
親御さんには、ぜひ小さい時から育んでほしい能力だと思うのです。
この試行錯誤力こそが、これからの長い学習において、最も重要な土台となるのですから。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


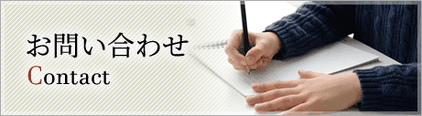
コメントをお書きください