
読解力の目指す「目的地」について、犬塚美輪先生は著書の中で、以下のように書かれています。
三つの目的地のうち、第一の目的地になるのが表象構築です。二つ目と三つ目は、(基本的には)この第一の目的地を経由しないとたどりつくことができない、二種類の「第二の目的地」と位置付けてよいでしょう。第二の目的地は、感動したり夢中になったりする「心を動かす」読解と、あえて納得しないことを選ぶ「批判」の読解です。
『読めば分かるは当たり前?読解力の認知心理学』(犬塚美輪/筑摩eブックス)
表象構築とは、「書いてある内容を頭の中で再現できること」です。
これには、書いてあることだけで完結する「テキストベース」の段階と、知っていることを活用した「状況モデル」の段階があると言います。
たとえば、
①大谷くんは野球の試合で、サヨナラホームランを打った。
という文であれば、「大谷くんは何をしましたか?」という質問に、テキストの内容を読むだけで答えることができます。
しかし、
②快音がスタジアムに鳴り響いた。大谷くんはゆっくりとダイヤモンドを回る。サヨナラだ。
という文でであれば、「快音」「スタジアム」「ダイヤモンド」という言葉から「野球」をしている状況だと見抜き、野球における「サヨナラ」という言葉が逆転勝ちを示す言葉であり、なおかつ「ゆっくりとダイヤモンドを回る」状況がホームランを示しているのだと類推する必要があります。
犬塚先生は、こうした表象構築ができるようになってから、心を動かす読解や批判的読解が可能になるというモデルを示されているわけです。

ただ、心がなんら動かない文章を読んで、表象構築はできるのでしょうか?
むしろ、最初に何らかの興味関心があり、自分にとって何らかの意味や価値を認めたところから表象構築ができるようになるのだと思います。
そうしたことから、アミラーゼ問題の正答率の低さは、「テストそのものや文章の内容への興味関心の薄さ」が一番の要因であったと私は考えているのです。
もちろん、興味関心の薄い内容の文章であっても理解するための訓練は必要ですが、それを訓練無しにできる人は少数であるということが言えますね。
その意味で、Moveで取り入れている「ことばの学校」は、興味関心に基づく読書の入り口として最適です。
まずは、心の動く、興味関心の持てる読書からスタートし、表象構築の力を身に付けていってもらいたいと思います。

進学空間Move塾長
宮脇慎也(Shinya Miyawaki)
27歳で広島大学社会科学研究科の博士課程後期日程を単位取得退学をし、その後学習塾の世界に飛び込む。
8年間の勤務講師としてみた広島の学習塾業界のあり方と大学院で養った知見との乖離に悩み、理想の学習塾を作るべく2013年に個別演習型の学習塾・進学空間Moveを立ち上げる。
その中で、モチベーションのあり方に着目し続ける中で、キャリア教育の重要性を認識し、キャリア教育と学習の融合を目指す。また、同時に保護者の方向けコミュニティー「Happy Education Lab.」を主催する。
1977年生。射手座。B型。
家族は妻と長男1人。趣味は広島発祥のスポーツ・エスキーテニス。


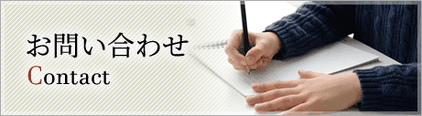
コメントをお書きください